
「自分の飲食店を持ちたい」と思い立っても、実際に開業するには多くの準備や手続きが必要です。コンセプトづくりから資金調達、物件契約、申請手続き、そしてオープン後の運営まで、一連の流れを把握しておくことが成功の第一歩です。
この記事では、飲食店開業を考える初心者オーナーに向けて、開業までの具体的なステップを解説します。さらに、開業後の安定経営につながる実践的なポイントまでまとめました。
飲食店開業の流れ

飲食店の開業は思い付きで進められるものではなく、明確な手順に沿って準備を進めることが成功への近道です。ここでは、初心者オーナーが押さえておくべき流れを具体的に紹介します。
ステップ1 コンセプトを決める
最初に取り組むことは、お店の方向性を示すコンセプトづくりです。どのような客層に来てほしいのか、どんな料理を中心に提供するのか、そして価格帯や雰囲気はどうするのかを具体的に言語化していきます。コンセプトが明確であれば、その後の物件探しやメニュー開発にも一貫性が生まれ、集客の軸をぶらさずにすみます。
ステップ2 事業計画を立てる
コンセプトが固まったら、数字に落とし込む作業が必要です。開業にどれくらいの資金が必要なのか、毎月の売上と支出のバランスはどうなるのか、利益を確保できる体制は整っているかをシミュレーションします。
まずは客単価を設定してみて、1日で何人、週に何人来るのかを考え、原価分や諸経費を引くことで、ざっくりとですが収支をイメージできます。この計画は融資を受ける際にも提出を求められるため、現実的で説得力のあるものにしておくことが重要です。
ステップ3 資金調達と予算設計
必要な費用が見えてきたら、資金をどのように調達するかを決めます。自己資金をベースに金融機関からの融資や自治体の補助金を組み合わせ、内装や設備、広告費などの用途ごとに予算を振り分けましょう。
計画段階で資金繰りをイメージしておくことで、開業後の資金不足を防ぐことができます。自己資金が少ない場合は費用を最低限に抑えるのか、資金を調達するのか考えなければなりません。
ステップ4 物件を探す・契約する
次に、実際に営業する場所を探します。立地や人通り、競合の有無などを総合的に判断し、売上予測と賃料のバランスが取れる物件を選ぶことがポイントです。理想的な立地はすぐに見つかるとは限らないため、複数の候補を比較検討しながら慎重に決める必要があります。
ステップ5 店舗設計・内装工事・設備導入
物件が決まれば、店舗の設計や内装工事に移ります。厨房の動線設計やホールのレイアウトは、日々のオペレーションに直結するため妥協は禁物です。さらに、コンセプトに合ったデザインに仕上げることで、来店したお客様にお店の世界観を感じてもらえるようになります。
ステップ6 POSレジ・キャッシュレス環境を整える
店舗づくりと同時に、会計や管理の仕組みを導入することも欠かせません。特にPOSレジは売上管理や在庫管理、人件費の把握などを一元化できるため、経営の基盤を支える存在となります。キャッシュレス決済に対応していれば顧客の利便性も高まり、会計スピードの向上やリピーター獲得にもつながります。
続きを見る

飲食店におすすめの無料POSレジ3選を表で比較|個人店・小規模店舗向け
ステップ7 スタッフ採用・教育
お店を運営するには、信頼できるスタッフの存在が不可欠です。採用段階から接客姿勢や協調性を見極め、採用後はマニュアルや研修を通じて一定のサービスレベルを維持できるよう教育していきます。開業初期は特にチームワークが重要になるため、早い段階から準備を整えておくことが大切です。
小さい店舗で少ない資金から始めるなら、固定費となる人件費をむりに割く必要なありません。1人で回せる広さの店舗を探し、無理のないオペレーションを組み立てましょう。
ステップ8 プレオープンからグランドオープンへ
準備が整ったら、いよいよ開店を迎えます。ただし、いきなり本番にするのではなく、プレオープンを設けて運営の流れを確認しておくと安心です。知人や限られたお客様に試験的に営業し、メニューの提供スピードや接客の流れを検証して改善します。
そのうえで迎えるグランドオープンは、完成度の高い状態でお客様をお迎えできる大切な日となるでしょう。
飲食店開業に必要な資格・届出・申請
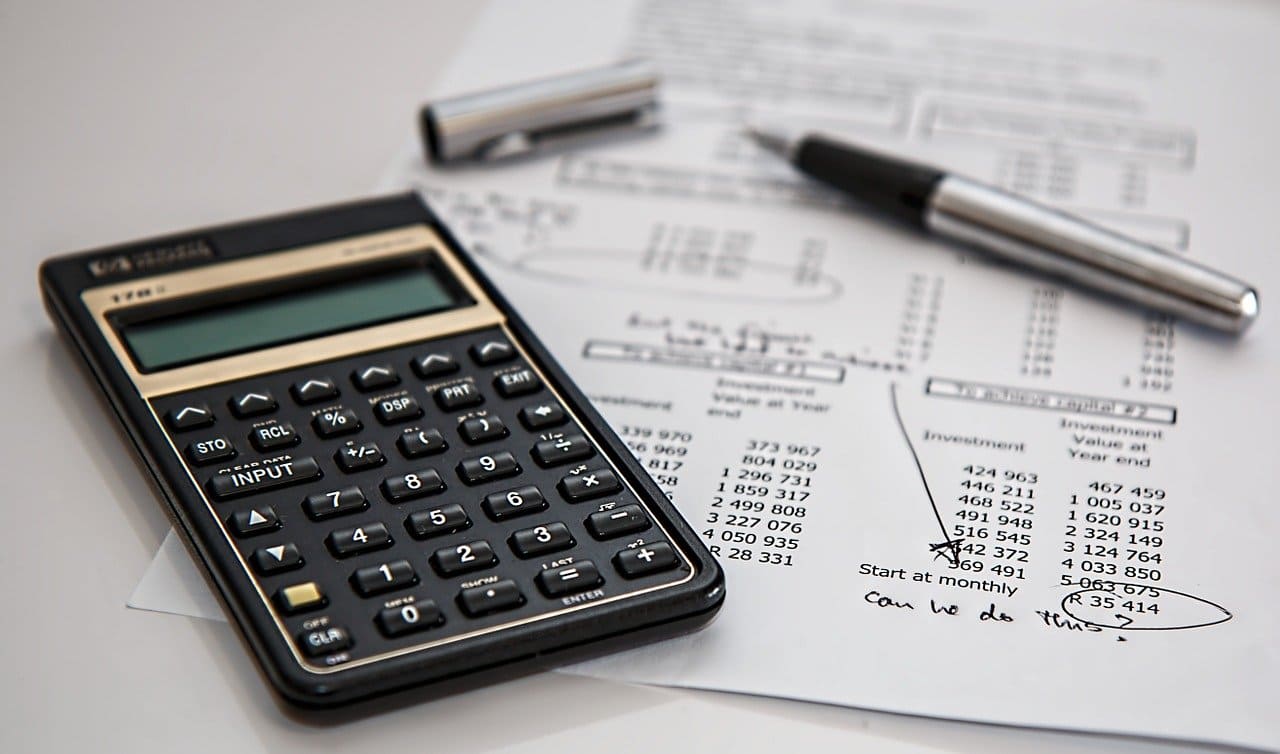
飲食店を始めるにあたっては、資金や物件の準備と同じくらい、法律で定められた資格や行政への手続きをきちんと行うことが欠かせません。これらを怠ると営業許可が下りなかったり、オープン直後にトラブルにつながる恐れがあります。
ここでは代表的な資格や届出について順を追って確認していきましょう。
食品衛生責任者
飲食店を営業するには、必ず店舗ごとに「食品衛生責任者」を置かなければなりません。各自治体の食品衛生協会が実施する講習会を受けることで取得でき、調理師や栄養士の資格を持っている場合は講習が免除されることもあります。営業許可を申請する際には必ず必要となるため、早めに取得しておくと安心です。
防火管理者・消防関連の手続き
火を扱う飲食店は、防火対策も厳しく求められます。客席が30人以上の店舗では「防火管理者」の選任が必要で、消防署への届出や消火設備の確認を受けることになります。場合によっては開業前に消防署の立入検査が入ることもあるため、内装工事の段階から消防基準を意識して準備を進めることが重要です。
深夜酒類提供営業の届出(必要な場合)
深夜0時を過ぎてお酒を提供する予定があるなら、警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出しなければなりません。
営業時間や提供方法、店内の配置などについて記載した書類を提出することが求められ、無届で深夜営業をすると法律違反に問われる恐れがあります。営業時間をどう設定するかを決める段階で、この届出の必要性を確認しておきましょう。
税務署に開業届を出すタイミング
営業許可の取得と並行して、税務署への「開業届」も忘れずに提出する必要があります。個人事業主の場合は、開業から1か月以内を目安に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するのが一般的です。
同時に「青色申告承認申請書」を出しておけば、帳簿を整えることで節税の恩恵も受けられます。法人として開業する場合は、法人設立届出書など別の書類も必要になるため、早めに確認して準備しておくと安心です。
飲食店開業にかかる費用の目安

飲食店を開業するには、物件取得から内装、設備、広告宣伝まで幅広い費用が発生します。特に初心者オーナーにとっては、どの段階でどれくらいの資金が必要になるのかをイメージしておくことが大切です。
初期費用(内装・設備・保証金など)
最も大きな割合を占めるのが初期費用です。物件を借りる際には保証金や敷金が必要になり、さらに店舗のコンセプトに合わせた内装工事や厨房設備の導入費がかかります。小規模な店舗であっても数百万円単位の出費になるケースが一般的で、飲食店の規模や立地によっては1,000万円以上必要になることも。
ただし田舎の場合や、そこまで修繕等の必要がない居抜き店舗などであれば、工夫次第で数十万円ほどで抑えられるケースもあります。
運転資金(家賃・人件費・仕入れなど)
オープン後に安定するまでの数か月間は、売上が見込み通りに上がらない場合もあります。その間に必要となるのが運転資金です。
家賃や光熱費、仕入れ、人件費など、固定的にかかる費用を3〜6か月分ほど確保しておくと安心です。特に飲食店は食材の仕入れや人件費の割合が高いため、予算を見誤ると資金繰りがすぐに厳しくなってしまいます。
資金調達の方法(自己資金・融資・補助金)
資金をどのように準備するかも重要な検討事項です。自己資金をベースに、日本政策金融公庫や銀行からの融資を組み合わせるのが一般的といえます。
最近では自治体による補助金や助成金を活用できるケースもあり、申請要件を満たせば初期費用の一部を軽減することも可能です。複数の方法を比較検討しながら、現実的な資金計画を立てることが成功につながります。
小さい飲食店なら資金ゼロでできるのか?

「資金がなくても飲食店を始められるのか」という疑問は、多くの人が抱いているでしょう。結論からいえば、全くのゼロで開業するのは難しいものの、低コストで始められる選択肢は存在します。
低コスト開業の選択肢(ゴーストレストラン・キッチンカー・自宅カフェ)
近年注目されているのが、店舗を構えずにデリバリー専用で営業するゴーストレストランです。既存の厨房を間借りしてスタートできるため、初期投資を大幅に抑えることが可能です。
また、キッチンカーでの営業や、自宅の一部を改装して小規模カフェを運営するなど、従来型の店舗よりも少ない資金で始められる方法もあります。
クラウドファンディングや補助金の活用
自己資金が足りない場合には、クラウドファンディングで出資を募ったり、自治体の補助金制度を活用する方法も有効です。
クラウドファンディングは開業前からお客様との接点を持てるというメリットがあり、応援者を集めながら資金調達ができます。補助金についても、設備投資や販促費に使える制度があるため、情報収集を怠らないことが大切です。
資金ゼロ開業のリスクと注意点
ただし「資金ゼロ」に近い形で開業すると、思わぬ出費に対応できなくなるリスクがあります。特に飲食店は食材費や人件費といった変動費が多く、資金に余裕がないと運営がすぐに行き詰まる懸念があります。
低コストで始める場合でも、最低限の運転資金や予備費は確保しておき、リスクに備えておくことが必要です。
経験ゼロから数十万円で小さな店舗を開業し、3年で繁盛店と認められ事業承継に至るまでの体験をまとめた電子書籍を販売しています。よければ参考にしてください。
続きを見る
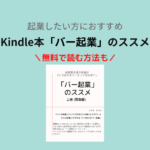
飲食店を経営・開業したい方におすすめの本!「バー起業」のススメ
開業における重要なポイント

飲食店の開業は、資金や物件探しだけではなく、その後の経営を見据えた仕組みづくりも大切です。ここでは特に初心者オーナーが意識しておきたい3つのポイントを紹介します。
キャッシュレス決済を導入する
飲食店を利用するお客様の多くが、現金よりもキャッシュレスを好む時代です。
クレジットカードやQRコード決済に対応していないと、せっかく来店したお客様が離れてしまうこともあります。開業時にPOSレジとセットでキャッシュレス決済を整えておけば、会計処理も効率化され、売上管理もスムーズになります。
飲食店向けのPOSレジサービスは以下の記事でまとめているので、ぜひ比較検討の参考にしてください。
続きを見る

2025|飲食店向けPOSレジのおすすめ12選&比較表!補助金の情報も
SNSからの導線を意識する
集客の柱となるのは、SNSやGoogleマップを活用した情報発信です。開業前からInstagramでメニューや内装の準備風景を発信したり、Googleビジネスプロフィールを登録しておくことで、オープン当日から集客につなげやすくなります。
SNS運用の基礎を学びたい方には、以下の電子書籍がおすすめです。初心者でも「どの媒体で何を投稿すればいいか」が明確になり、実際の運用に役立ちます。
飲食店のための Web集客活用法 & Instagram攻略
経営をなんとなく始めては危険
「料理が好きだから」「自分の店を持ちたいから」といった思いだけで開業すると、経営が長続きしないケースも少なくありません。飲食店は原価率や人件費、回転率などを常に意識し、戦略的に運営する必要があります。
そのためには、基本的なマーケティング知識を身につけておくことが欠かせません。以下の書籍は飲食店に特化したマーケティング戦略の入門書です。感覚ではなく数値と仕組みに基づいた経営をするためには、ぜひご覧ください。
まとめ|開業成功のために準備すべきこと
飲食店を開業するには、コンセプトづくりから事業計画、資金調達、物件契約、資格取得、そして店舗運営に至るまで、多くのステップを踏む必要があります。小規模店舗であれば低コストで始める方法もありますが、資金ゼロに近い形での開業には大きなリスクが伴うため注意が必要です。
さらに、開業後の経営を安定させるためには、キャッシュレス決済の導入やSNSを活用した集客など、現代の飲食店経営に不可欠な仕組みを整えておくことが重要です。そして何より、感覚に頼るのではなく、マーケティング知識を活用しながら数値に基づいた運営を行う姿勢が、長く続くお店づくりにつながります。
飲食店の開業は大きな挑戦ですが、計画的な準備と継続的な学びを重ねれば、理想のお店を実現することは十分に可能です。
おすすめのPOSサービスをまとめた記事や、飲食店オーナーにおすすめの書籍をまとめた記事もあるので、ぜひあわせて参考にしてください。
続きを見る
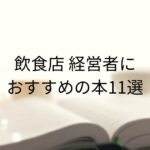
飲食店経営者におすすめの本11選!開業に興味がある人も必見
続きを見る

2025|飲食店向けPOSレジのおすすめ12選&比較表!補助金の情報も
続きを見る

飲食店におすすめの無料POSレジ3選を表で比較|個人店・小規模店舗向け

